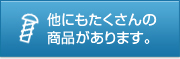- 低頭・小頭

- 六角穴付

- ボルト

- 小ねじ・マイクロねじ

- タッピングねじ


-
- (+)B1なべ タッピング(2種)
- (+)B1皿 タッピング(2種)
- (+)B1皿 タッピング(2種) D=6(小頭)
- (+)B1皿 タッピング(2種) D=7(小頭)
- (+)B1トラス タッピング(2種)
- (+)B1バインド タッピング(2種)
- (+)B1丸皿 タッピング(2種)
- (+)B1なべ タッピング ワッシャーヘッド(2種)
- (+)B0なべ タッピング(2種)
- (+)B0バインド タッピング(2種)
- (+)B0皿 タッピング(2種)
- (+)B0皿 タッピング(2種) D=6(小頭)
- (+)B0皿 タッピング(2種) D=7(小頭)
- (+)B0トラス タッピング(2種)
- (+)B0なべ タッピング ワッシャーヘッド(2種)
- ワッシャー

- ナット

- 座金組込みねじ

- 手締めねじ

- 止め輪・ピン

- ドリルねじ

- アンカー

- リベット

- 建物金物

- 機械部品・工具

- 樹脂製品

- パック商品

- TOP >
- ネジ・ボルトの図書館
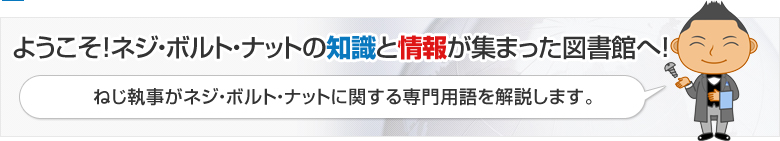
| 矢打ち | 焼入れ | やきつかナット | 焼付き・焼き付き(かじり) | 焼なまし | 焼ならし | |
| 焼戻し | 山形座金 | 山数 | 有効径 | 有効ねじ長さ | ユニクロ | |
| ユニファイねじ | ユリヤ樹脂 | 陽極酸化処理 | 溶融亜鉛めっき | 呼び径 |
矢打ち
ねじの頭部へ六角穴などを成形する加工を表します。切削によるプレス加工で成形する際は、前処理(下穴)として六角の対辺と同じ大きさ(径)のキリ穴を有効深さより深く開ける必要がありますので、穴深さを多めに考慮しなければいけません。
焼入れ
鋼を適当な温度まで急加熱してオーステナイト状にした後、冷却油などでマルテンサイト状になるまで急冷させる熱処理の事です。ただし、この状態では非常に強固ですが脆い性質なので、必ず焼戻しを行います。
焼入れ焼戻し(調質)記号は(Q)。
やきつかナット
通常、ステンレスはトルク(ねじとしてはねじ込む力)が高い場合など、焼付きが発生します。この焼付きを防止する為、コーティングなどを行いますが、許容域を超えるトルクでねじ込むと焼付きが起こります。その許容範囲を大幅に広げたナットがやきつかナットです。
やきつかナットの詳細はこちら
焼付き・焼き付き(かじり)
ステンレスの熱が発生しやすく逃げにくいという性質から、高トルクでボルトとナットの締結作業を行うと、その摩擦熱により素材が膨張し、おねじとめねじが圧迫されねじが回らなくなります。この現象を『焼付き(かじり)』といいます。焼付きと記載される場合もあります。
この焼付きの原因となる摩擦熱を抑える為に、ナットなどに焼付き防止コーティングを行います。ただし、高トルクや繰り返し使用の場合、焼付きが起こりますので注意が必要です。
焼なまし
加熱した温度からごくゆっくり冷やし、鋼を軟らかくする熱処理です。鉄の内部の応力を除去してひずみを無くすためにも使われます。焼鈍とも呼ばれます。
焼なまし記号は(A)。
焼ならし
加熱後の冷却によって不均一になった組織を微細化し、均一な標準状態の組織(パーライト組織)にする処理の事です。焼準とも呼ばれます。
焼ならし記号は(N)。
焼戻し
焼入れをした鋼は非常に硬いが脆い為、再び加熱することによって靱性を持たせる処理をいいます。
山形座金
ローゼットワッシャー参照。
山数
山数とは、ウィット規格やユニファイ規格などで使用され、1インチ(約25.4mm)あたりに含まれるねじ山の数を表します。
メートルねじでいうところの“ピッチ”と同様の意味合いになります。
有効径
定義はねじの谷の幅がねじ山の幅に等しくなるような仮想的な円筒の直径と規定されています。おねじとめねじの有効径の差が少ないとしっかりとはまり、大きいとガタが大きくなります。
有効ねじ長さ
有効ねじ長さとは、不完全ねじ部を除くねじ部が形成されている長さを表します。ボルトなどの場合は先端の面取りも有効長さに含まれます。
ユニクロ
表面処理の名称のひとつで、表面は水色がかった色をしています。電解亜鉛メッキ後にクロメート処理を行います。耐食性は有色クロメートより劣ります。主に装飾用として用いられます。「光沢クロメート」「中和クロメート」とも呼ばれます。
※こちらは六価ユニクロとも呼ばれ、現在は欧州などで規制対象物質が制定(RoHS指令等)されており、対象物質となる六価クロムの含有量が制限量を超えておりますので、非対応となります。
RoHS対応向けの代替としては“三価クロメート(三価ホワイト・三価ユニクロ)”になります。
ユニファイねじ
インチねじの一種となりANSI規格によるねじで、ピッチを1インチ(=25.4mm)に対して山数で表します。ねじ山の角度はメートルねじと同じ60°です。並目ねじ(UNC)と細目ねじ(UNF)で表され、ねじ径の後ろにピッチを記載される事が多いです。
(例) 3/8-16UNCx1-1/2(並目) 3/8-24UNFx1-1/2(細目)
ユニファイ規格についてはこちらからご確認いただけます。
ユニファイねじのご購入はこちらから
ユリヤ樹脂
尿素樹脂とも呼ばれるユリヤ樹脂は、尿素とホルムアルデヒドとの反応によって生成される安価で燃えにくい熱硬化性樹脂です。ユリヤ樹脂は接着性が良い、常温で接着が可能、また硬化速度も早い事からほとんどが接着剤の原料とされています。電気的性能にも優れていて着色も可能、表面硬度が高くプラスチック成型品としても利用されていますが、反面、耐薬品性・耐熱水性・耐衝撃性が弱くクラックが入りやすい、湿度などによる寸法変化も大きいとデメリットもあります。また近年では環境による含有物規制が厳しく、ユリヤ樹脂に含まれるホルムアルデヒドがその対象になっていますので、利用が制限されています。
陽極酸化処理
アルマイト処理参照。
溶融亜鉛めっき
一般的にはドブメッキと呼ばれます。その名の通り、溶かした亜鉛に素材を浸して付けるめっきの事です。防食性は非常に高いですが、電解メッキに比べると膜厚が非常に厚く(一般の電気めっき 約3〜5ミクロンに対し、ドブめっき 約50ミクロン)、均等性も低くなります。また膜厚が厚い為、オーバータップ(太口)された雌ねじを使用する必要があります。
溶融亜鉛めっきは処理時に400度以上の高温になる為、六角穴付ボルト(キャップボルト)などの熱処理された商品には向いていません。
天ぷらの衣のようにめっきが付く事から“天ぷら(テンプラ)めっき”と呼ばれる場合もあります。
※めっき厚が厚く、不均等なのでゲージ管理はできません。
呼び径
呼び径とは、おねじを基本としたねじの直径(外径)の事をいいます。“ねじの呼び”と呼ばれる事もあります。